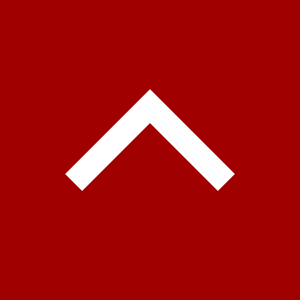

誰も知らない、あの男の《はじまりの日》を描く
プログレッシブストーリー
-
Chapter 1
Chapter 1
「……これが《アインクラッド》、ねぇ」
果てしなく広がる青空に純白の雲、色鮮やかな草花、頬を撫でるそよ風、やや古めかしい街並と足裏に伝わる石畳の感触。
全ては脳に送り込まれたデジタルデータに過ぎないのだと改めて意識しても、なおゲームの世界だとは信じ難い。
それほどのリアリティがある。
なるほど、確かに最先端の科学技術ではあるのだろう。だが──
やはりこれは作りものだ、と彼は思う。
空気は反吐と汚水と排泄物の悪臭に満ち、道路にはゴミと汚物が散乱、建物の壁は落書きで彩られ、
喧噪は絶えることなく日常的に怒鳴り声や悲鳴が響き渡る。
少なくとも彼が十五まで育った世界では、郷愁など抱きようもないそんな光景が当たり前のものだった。
この《はじまりの街》には、現実のにおいが無い。
設計者の意思に基づいたわざとらしい清潔さ、いわば──そう、《嘘》に満ちているのだ。
ヴァサゴ・カザルス/PoHは、とある非合法組織に所属する暗殺者である。
デスゲームの舞台と化した《SAO》には、
現実世界において手が出せない標的を始末するのに絶好の条件が整っている──
そう判断した組織の上層部により、この仮想世界に送り込まれてきたのだ。
もっとも実行役としては、まったくもって容易な仕事とは思えなかったわけだが。
「……ったく、クソッたれな命令を下すだけの立場は気楽でいいよな」
さて、どうしたものか。
ダイブするにあたり《SAO》について可能な限りの知識を詰め込んでは来たが、
それでもこのゲームを十分に知っているとは言い難い。
茅場とかいうイカレたゲームデザイナーが大騒動を引き起こしてからすでにそれなりの日数が経過しているし、
きっと状況も色々と変化していることだろう。
であれば、まずは情報収集だが──と、周囲を見回したそのとき。
「やあ、そこの人、何か困ってるのかい?」
爽やかな口調でそんな言葉を掛けられた。
視線を巡らせると、二人組の男と目が合った。
「──今俺たちが受注したのは、報酬に金(コル)を入手できる金策クエ。定期的に発生するやつで、
内容はシンプルなモンスター討伐。指定された場所にランダムな低レベルモンスターが現れ、
それを適当に倒せばクリアって仕様だ」
草原を歩みながら、長身の剣士は説明した。
「クエストは色々あるが、まあ最初はこういうのから始めるのが無難だな」
年齢はおそらく二十歳前後。快活な表情やまっすぐに伸びた背筋から、闊達な気性がうかがえる。
最初に声を掛けてきたのもこの男だ。
表示されているキャラクターネームは《Castor》。
「ソロで挑んでもいいんだけど、基本的にはこうしてパーティーを組んだ方が効率いいよ。
倒した数によって報酬が上乗せされたりするしね」
小柄な男が愛想のない口調で続ける。
見た感じ相棒より三つ四つ年下。やや軽装で、索敵や斥候寄りのビルドだろうか。
キャラクターネームは《Pollux》。
「ああ、そういや自己紹介がまだだったな。俺がカストール、そいつがポルクスだ」
「確かギリシャ神話の双子の名前だっけか。ってことは、アンタら兄弟?」
「血は繋がってないが、それに近い関係ではあるかな。長年の相棒だ。一目でコンビだとわかるいいネーミングだろ?」
「……そういうことを、初対面の人にペラペラ話すなよ、恥ずかしい」
「何だよ、名前決めたのはお前じゃないか」
「だから、そういうのが恥ずかしいんだって!」
拗ねたように言い、ポルクスはぷいと横を向く。
「気難しい奴で悪いね。で、あんたは《PoH》……読みはプーでいいのか? その、ずいぶんと可愛らしい名前だな」
「親からもらった大切な本名由来なんだぜ?」
PoHはニヤリと笑みを浮かべる。親しみやすく見えるよう計算された表情だ。
「──しっかし、わざわざパーティーまで組んでクエスト世話してくれるとか、親切なことだなぁ。
オレにとっちゃありがたいんだが、大して戦力にならない初心者(ニュービー)に構って、
アンタらに何のメリットがあるんだ?」
何らかの計略や詐欺である可能性は最初に疑ったが、その考えをPoHは早々に放棄していた。
彼らが街の《アンチクリミナルコード有効圏内》──つまり安全地帯を出てプレイヤー同士が殺し合えるエリアに入っても、
こちらをまったく警戒していなかったからだ。
この二人はPoHが牙を剥いてきたり、あるいは逃走してしまうことを想定していない。
獲物を罠に捕らえたつもりなら、こんな平穏にどっぷりと浸り切ったような態度にはならないものである。
「声かけたのはあんたが困ってそうだからだけど……」
答えたのはカストールだった。
「ま、確かに単なる親切心ってわけでもないな。──なあPoH、あんたは今の《はじまりの街》を見てどう思う?」
「どう?」
嘘くささが鼻につく、というのが正直な感想だが、おそらく求められているのはそういうことではないのだろう。
少し考えてからPoHは口を開いた。
「……活気がねぇな」
「そうなんだ」
我が意を得たりというようにカストールは肯く。
「死の恐怖で身動きの取れなくなったプレイヤーが大勢居る。ベータテスターを中心に先へ進んだ連中もいるが、
数は多くない。いくら何でも彼らだけでこのゲームをクリアするのは無理だろう。態勢を整え直す必要がある」
「あん? つまりアンタはプレイヤーたちをまとめ上げ、クリアを狙うってのか?」
「リーダーを気取るつもりはないさ。でも、可能なら皆でクリアを目指すべきだとは思ってる。
そのために、まずはプレイヤーの底上げをしたいんだ。つまり……皆の気力を取り戻し、蔓延する諦観を一掃する」
「余計なお世話だと思うけどね」
ぼそりとポルクスが口を挟んだ。
「カストールにはわからないかもしれないけど、人間、どうしてもポジティブになれなくて、
放っておいて欲しいって気分になることもあるんだよ」
「それはそうかもしれないが……ただ待ってたって、何も変わらないぞ?
逆に動ける奴らが増えて、その何割かでもクリアを目指すようになれば、攻略組の層も厚くなる」
「で、オレは見込みアリと判定されたわけか?」
「ああ。だって、街中で困った様子ってことは、少なくとも自ら動いて何かやろうとする意思を持っているわけだろ?
なら手を貸す価値はある。──さ、そろそろ目的地だ」
Continued... -
Chapter 2
Chapter 2
外見の印象通り、ポルクスが索敵、カストールが戦闘と役割を分担しているようだった。
特にカストールはなかなかの腕前で、昆虫型のモンスター数匹を独力で危なげなく倒してみせた。
「……また全部持って行かれた。たまには僕にも戦わせてほしいんだけど」
「もう少し我慢しろ。時期が来たら、俺が指示してやるから。だいたい戦闘をするなら、
先にレベルを上げてステータスを伸ばしてからの方が安全だろ? なんせ命が懸かってるんだからな」
「わ、わかってるよ。でも、だったらお前も危険じゃん」
「俺は強いからいいんだよ。適材適所だ」
笑顔で一蹴され、不承不承という様子ながらもポルクスは黙った。
戦闘に参加しないプレイヤーには、当然ながら戦闘経験値は入らない。ポルクスの不満はそこに由来するものなのだろう。
とはいえ、パーティー用クエストのクリアボーナス経験値はしっかり全員に配分されるため、
戦闘のみがレベリングの手段というわけでもない。
おかげで、カストールの戦いを見物していただけのPoHも恩恵に与ることができる。
「……オレからアンタらに提供できる見返りは何もねぇぞ?」
「構わないさ。ま、これからも協力できれば嬉しいが、あんたはあんたで好きなことをやればいい。
戦闘を極めるにしろ生産職に就くにしろ、やりたいことが見つかればそれは生き抜く力になる。
さっきも言ったが、そういう奴が増えたらきっと何かが変わると思うんだよ」
──前向きなことだな。
いささか皮肉っぽい感想を抱きつつ、PoHは内心で肩をすくめた。
少なくとも《仕事》のためにこの世界へとやってきた自分には、関係のない話である。
「……森の方からもう一匹来る!」
そのとき、ポルクスが緊張を孕んだ声で告げた。
ほどなくカストールとPoHの視界にも植物型のモンスターが姿を現す。
「──《リトルネペント》? クエストのターゲットではあるが、初めて見るモンスターだな」
そう呟きながらカストールは抜剣した。
「ちょっと一戦交えてみる。報酬もモンスターの情報も、多くて困ることはないだろう」
「だったら僕も──」
「二人はここでしばらく待っていてくれ」
「……またかよ。相手は一匹だけなんだし、僕だって戦えるよ」
「PoHを一人にするわけにはいかないだろう? カーソル色で判断する限り、敵のレベルは高くない。
厄介な特殊攻撃でも持ってるようなら、さっさと逃げ出してくるさ」
そのままカストールはモンスターの方へと向かい、取り残された形になったポルクスは苛立たしげに小さく舌打ちした。
《リトルネペント》の体高は人間と同じくらい。やや縦長な壷状の胴の上部に大きな口。その上には頭部(?)を飾るように丸い実が付いている。無数の根を使って器用に移動するが、動きそのものは対処に困るほど速くはない。
主な攻撃手段は両腕のツタか。今のところカストールは上手く捌いているようだ。
「…………」
ポルクスはどこか不機嫌そうに戦いを見つめている。
PoHは少し思案し、彼に声をかけた。
「なあ、もしかしてアンタがカストールをこのゲームに巻き込んだのか?」
「────!」
ポルクスは弾かれたようにこちらを向いた。
「な──ど、どうして……!?」
「いや、別に大した根拠があるわけじゃなかったんだがな。リアルでもずいぶんと親しいようなのに、
なぜかアンタからは不自然な負い目が、ヤツからは過剰気味な気遣いが感じられた。図星だったか?」
「…………」
おそらくは固有の特殊攻撃なのだろう、《リトルネペント》はその大きな口から薄緑色の液体を吐き出した。
しかし、これもカストールは機敏に回避する。
ポルクスは視線を相棒の方に戻し、やがてぽつりぽつりと語り出した。
「……ご近所の幼馴染みってやつだ。母親同士が友人でさ。兄弟同然、と言ってもあながち間違いじゃないだろうな。
昔から兄貴風吹かせる奴ではあったし」
カストールは幼い頃から優秀で、現在は名の知れた大学に通っているらしい。
一方、三つ年下のポルクスは、学校に馴染めず休みがちな高校生とのことだった。
共通の趣味であるゲームを通じ、二人の付き合いは幼い頃から途切れることなく続いていた。
ある日、ナーヴギアと《SAO》の存在を知ったポルクスは、最も親しいゲーム仲間であるカストールを誘った。
就職活動中で多忙だったカストールは当初渋ったが、
ポルクスの熱意に負けて彼と共に《SAO》へとダイブすることを承諾した。
そして──二人はこの事件に巻き込まれた。
「……あいつは恨み言一つ言わず、僕を見捨てることもしなかった。僕より要領は良いしレベルは上だし、
もっと強い奴や頼りになる奴を相棒にすることだってできたはずなのに」
──強く優しい理想の兄、固く美しい兄弟の絆ってか。
無意識のうちにPoHは体の左側、無くなった腎臓の位置をそっと押さえていた。
自分と異母兄との、か細い繋がり。
もちろんアバターには内臓も手術痕も存在しないのであるが。
「守られてるのはわかる。感謝してないわけじゃない。でも……それじゃ僕は一生このままなんだ。
償う機会すら与えられない。絶対に消えない引け目を感じ続けなきゃいけない。そのくらいなら──」
いっそ見捨ててくれた方が楽なのに、と絞り出すような声で言う。
「つまりアンタは現状に甘んじていたくねぇ、と」
「あ、ああ、それはもちろんだけど……」
「だったら一つ、いいこと教えてやろう。アンタとカストールが対等になる手助け、引け目を解消しちまう方法だ」
ポルクスは複雑な表情を浮かべた。不審と関心が半々というところか。
「よく聞けよ? あの《リトルネペント》には大きな弱点がある。ちょっと勇気出してそこを叩いてやりゃあ、
一撃で倒すことができるんだ。上手く決めれば、アイツもアンタを見直すはず。
そしたら、対等の相棒へと一歩を踏み出せるだろ?」
「じ、弱点? 本当か? ってか、なんであんたがそんなこと──」
「そんなことを知ってるのかって? ……実はオレがベータテスターだからだよ」
ポルクスは小さく息を呑んだ。
「目立ったり面倒に巻き込まれるのはご免だから黙ってたんだが……アンタたちには親切にしてもらったからな。
ささやかな恩返しだ。──どうだ? 続きを聞くかい?」
「…………」
無言でPoHをまっすぐに見つめ、やがてポルクスは肯いた。
Continued... -
Chapter 3
Chapter 3
空気を切り裂くような絶叫が響き渡り、そして唐突に途絶えた。
「……さぁて、終わったか?」
一人で安全圏まで退避していたPoHは、腰を上げのんびりと歩き始める。
先ほど、PoHはポルクスに対し二つの嘘をついた。
一つ、PoHはベータテスターではない。
とはいえ、ベータテストの知識はある程度有している。事前に組織が集めてきた《SAO》の情報には、
ベータテスターを介して入手したものも多分に含まれていたからだ。《リトルネペント》のこともその中にあった。
二つ、PoHがポルクスに教えたのは、《リトルネペント》の弱点ではない。
では何だったのかというと──
「お? こっちはしぶとく生き残ってたか」
PoHの視線の先、長身の剣士が虚脱した様子で立ち尽くしていた。
「……あ、あんた、か……」
カストールはのろのろと顔を上げた。その表情からは、およそ生気というものが感じられない。
つい先刻までの強い意志力と揺るぎない自信は、もはやどこにも存在していなかった。
「ポルクスが、いきなり割り込んできて……モンスターの頭の実を割ったんだ。
そうしたら……同種のモンスターが……数え切れないくらい、集まってきて……守り切れず……」
そう、《リトルネペント》の実には、破壊されると煙をまき散らしエリア内の同族を呼び集める、という特性がある。
弱点などではなく、むしろ悪辣なトラップの一種だ。
「すまねぇ、突然のことでオレも止められなかった」
可能な限りの沈痛な口調を作り、PoHは言った。
「アンタの戦いを見てるうち、どうも何かが限界を超えちまったらしくてな。自暴自棄な叫び声を上げて、飛び出していった。
まさかアンタを巻き込んで自殺を図るとは……」
「…………」
「なあ、何か心当たりはねぇか? ちょっと話した感じ、アンタと一緒に戦うのを拒絶されたことが
相当こたえたようだったが……」
「…………! そんな……!」
巨大モンスターの一撃を食らったかのように、カストールはよろめいた。
剣を杖のように突き立て、しかしそれでも体を支えきることはできず地面に両膝を突く。
「お、俺はただ、あいつが危険な目に遭わないように、と……それが……かえって、あいつを傷つけてたのか……?
だから、俺を巻き込んで、死のう、と……? 俺は……あいつを、元の世界に返してやりたくて……ただ、それだけで……。
なら、俺の、俺のやってきたことには、何の意味が……」
「………………ふん」
放心状態でいつまでもブツブツと呟き続けるカストールに、PoHは気持ちが冷めていくのを感じていた。
落ちていたポルクスの剣を拾い上げ、鎧の隙間から無造作に刺す。
それでわずかに残っていたHPが0になった。
「あ、あ……?」
何が起きたのかわからないというように目を瞬かせると、カストールは死亡エフェクトに包まれ消滅した。
血は流れず死体も残らず……殺人者に何の実感も残さないまま、一つの命がついえる。
「最初に《実》付きを引き当てちまった運のクソ悪さは同情に値するとしても、だ。──そうじゃねぇだろ、カストールさんよ」
PoHは言葉と共に失望のため息を吐き出した。
「世界の空気を変えたいってんなら、こんな挫折ごときで壊れてちゃ駄目じゃねぇか。なんでさっさと立ち上がらねぇんだよ。犠牲は乗り越えてこそ意味があるってもんだろうが」
だいたい、PoHとポルクスの間にどんなやりとりがあったのかとか、ポルクスは《リトルネペント》の実の話を
どこから聞いたのかとか、疑念を抱くべきポイントは幾らでもあったはずだ。
それこそポルクスを唆した者、復讐すべき相手が目の前に居るという真実に辿り着くことだって
決して難しくなかっただろう。だというのに──
「長年つきあってきた弟分のことより、オレの話をあっさり真に受けちまうとはな。その心の弱さには心底ガッカリだよ。
──そもそもアンタが弟を本当に大切に思っていて、普段からしっかりと向き合っていれば、
ヤツがオレの口車に乗せられることもなかったはずなのにな」
結局、高邁な理想も兄弟の絆も、あっさり崩れ去るだけの偽物。
意図してこういう方向に誘導したのは自分であるが、
予想から一ミリも外れない結末というのは今ひとつ満たされないものだと思った。
「世界が偽物なら、人の心も嘘まみれ、か。……いや、嘘を剥ぎ取り、本質を露わにする世界と言った方が適切かねぇ」
いずれにせよ、仕事とは関係ないことで時間を浪費してしまった。
──余計な手間まで掛けて、いったい何がやりたかったんだ、オレは。
自嘲気味に唇を歪め、そして……ふとPoHは眉をひそめる。
自分には《やるべきこと》がある。そのためにこの世界にやってきたのだから。
では……《やりたいこと》はどうだろう?
カストールとポルクスに興味を覚えたのは確かだ。結果としては期待外れだったが、それでも彼ら──父や兄と同国の人間が無様で無意味な死を迎える様には爽快感があった。
──また味わってみたいという、この欲求がそうなのだろうか?
「…………次は、もっと人を集めてみるか」
我知らず口の端が吊り上がっていた。
あの二人を手玉に取ったように、今度は更に大勢を踊らせる。
そして、標的以外にも可能な限り多くの日本人プレイヤーを殺すのだ。
死がすぐ隣にあるこの世界は、たやすく人の本性を剥き出しにし、その《嘘》を暴いてくれるに違いない。
愉悦の予感に胸を弾ませつつ、しかし一方でPoHは自らの内にある問いが生まれるのを感じていた。すなわち──
もし、もしも……クソどもの中に決して折れない強靱な意志、穢されることのない真なる魂を見出したら、どうする?
そんなことあるわけがないと思いつつ、答えは驚くほどすんなりと導き出された。
──オレはそいつを熱烈に愛してやるさ。
そう、全身全霊をかけ、自らの手で跡形もなく壊してしまうくらいに激しく。
これはきっと永遠に消えることのない渇望、どんな世界に何度生まれ変わろうと熱を失わない心の熾火だ。
自分はおそらく、生涯《本物(リアル)》に惹かれ執着し続けるのだろう。
そういえばかつて、カストールがこんなことを言っていた。
──あんたはあんたで好きなことをやればいい。戦闘を極めるにしろ生産職に就くにしろ、やりたいことが見つかれば、
それが生き抜く力になる。
「……つまらねぇ奴だったが、その言葉だけは正鵠を射てたぜ」
システムメニューが示す日付は2022年11月21日。
やりたいことは見つかった。《Prince of Hell》の楽しい人生が、今日ここから始まるのだ。
二人の遺品からめぼしいものを拾い上げつつ、PoHは上機嫌で鼻歌を口ずさんだ。
Fin...